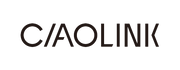桜とわたし
長尾衣里子
はじめに
京都の春といえば、“桜”です。
この時期の京都では、東西南北どこへ行っても桜を愛でることができます。在京10年が経ち、蕾の膨らむ桜木を見ると「ああ、今年もお腹いっぱい桜を堪能できる時期が来るな」と感じます。わざわざお花見に行かなくても、近所を散歩したり通勤途中だったり、日々の行動圏内に沢山の桜が咲いているのです。つまり、京都に住む人にとっては、他の日本の地域と同様に日常の中に桜があるのです。
一方で、京都の春といえば「桜と寺社仏閣」「桜と和菓子」「桜とおばんざい」「桜と着物」など、京都文化と言われるあらゆる事柄が、桜とコラボレーションする時期でもあります。そして、一年で最も多くの人が桜を見るために京都を訪れます。観光客気分で京都に住みはじめた最初の2-3年間は、京都の春を堪能した証としてこのようなラインナップの「桜と〇〇」を写真や動画で切り取りiPhoneに収めていました。けれども4年目辺りから、このような写真を全く撮らなくなり、日常でたまたま出会って美しいと感じた桜だけを残すようになりました。なぜ、京都に住む人にとっては日常の一部である“桜”が、こんなにも特別視されるのでしょうか?

画像1 朝の通勤路
桜と現代アート
さて、“桜”で現代アートといえば、思い出すのは2024年に開催された現代美術家・村上隆の大規模個展「村上隆 もののけ 京都」(京都市京セラ美術館)です。この展覧会の最初のインパクトは、中央ホールにあったインスタレーションです。美術館のメインエントランスから大階段を登ると、ホールに設置された巨大な2体の鬼の彫刻《阿像》《吽像》(ともに2014年)がお出迎え。鬼たちの背後の壁一面は満開の桜のビジュアルで覆われていて、まさに圧巻でした。
このコラムを書くにあたり、村上隆の“桜”が見たくてiPhoneの写真データを漁ったのですが、なんと撮っていませんでした。自分で自分が信じられません。そして驚くことに、会期中3-4回美術館に来ていた夫もこの満開の桜を写真に収めていませんでした。なぜ撮っていなかったのか?!私の場合、この美術館は勤務先です。毎日のように村上隆の“桜”を見ていました。いつも眺めていたので、特別写真を撮ろうという気持ちにならなかったのだと思います。京都出身の夫は「京都に住んでると仁王像や桜は当たり前にある存在やし、わざわざ写真に残そうと思わへんかったんちゃう」と言っていました。あまりに日常すぎて特別視することがない、それが京都に暮らす人々の認識なのかもしれません。
ですが、村上隆は、京都の春を表現するにあたり、満開の桜の光景を切り取り作品化しました。古来絵師たちが活躍した京都に深い関心を持ち続けてきた村上隆だからこそ、芸術家としての視点から、京都の日常を美しく彩る桜の存在に気が付き「桜と鬼の彫刻《阿像》《吽像》」という形で京都の春を表現したのではないでしょうか。
 画像2 「村上隆 もののけ 京都」展示風景、京都市京セラ美術館 2024年
画像2 「村上隆 もののけ 京都」展示風景、京都市京セラ美術館 2024年
Photo: KOZO TAKAYAMA
©2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.
桜と日常
さて、“桜”で日常といえば、人間国宝であった京都を代表する型絵染[1]作家、稲垣稔次郎の《御室の塔》(1961年)を思い出します。稲垣は、生まれ育った京都での日々の暮らしを大切にし、その中から自然に浮かぶ風景や物事をモチーフにして表現しました。稲垣は「物を創る本当のあり方は、環境が主体となっていることだ」と言います。作家自身を取り巻く環境を主体として創造するという、稲垣独自の見方や制作理念があったのです。では、稲垣はどんな春の日常を表現したのでしょうか?《御室の塔》の舞台は京都の仁和寺[2]です。桜の名所として知られており、そのなかでも「御室桜」と呼ばれる桜の林が有名で、1924年に国の名勝に指定されています。樹木の高さがやや低いのが特徴で、桜の花が雲海のように境内を覆っています。稲垣は、その満開の桜の林を若い息子とその婚約者がともに歩んでいく姿を描きました。
 画像3 稲垣稔次郎《御室の塔》(1961年)
画像3 稲垣稔次郎《御室の塔》(1961年)
©INAGAKI DESIGN
そういえば春になると、勤務中に若い婚約カップルの前撮り(あるいは後撮り)[3]の場面に度々遭遇します。彼らは結婚式さながらに婚礼衣装を身にまとい、寄り添い笑みを浮かべて撮影をしています。どのカップルも幸せそうで、目の前に広がる未来に希望をもっているように見えます。京都市京セラ美術館とその付近(平安神宮や琵琶湖疎水など)は、京都の観光名所として知られており、記念写真のロケーションとして選ばれることが多いようです。特に春になると「桜と美術館」「桜と庭園」「桜と鳥居」といったシチュエーションの記念写真が人気のようで、毎日のように撮影している婚約カップルを見かけます。もしかしたら稲垣も表現した「桜と新婚さん」は昔から京都の春の風物詩として存在するのかもしれません。
桜と風物詩
さて、春の風物詩で“桜”といえば、春の伝統行事である三月三日の桃の節句が思い浮かびます。雛人形を飾って子どもの成長と幸せを願いお祝いする習わしです。雛人形を出す時に桜と橘の花木も飾るのですが、左右どちらに置くか迷った経験はありませんか?これは、元を辿ると京都御所に由来しています。京都御所の紫宸殿の南庭には、東に桜、西に橘が植えられています。宮中の警固などを行う近衛府である左近衛・右近衛が、この桜と橘の近くに配陣されていたことから「左近の桜、右近の橘」と呼ばれるようになりました。つまり、雛人形(天皇であるお殿さまと皇后であるお雛さま)から見て、左側に桜、右側に橘を飾るのが正しい置き方なのです。桜と橘はどちらも魔除けの花とされており、平安時代の宮中では霊力があるとされていました。
宮廷の重要な儀式が行われた場所である紫宸殿は通年公開しているのでいつでも見られますし、春の特別公開では宮廷文化である雅楽や蹴鞠といった催しと共に堪能することもできます。そして京都御所は、春には桜、梅、桃が同時に咲く隠れた花の名所として知られています。
余談ですが、京都御所の話になると京都の人たちは冗談まじりに(けれども本気で)「天皇さんはいつになったら帰ってきはるんやろ?」と言います。常套句なのです。京都が都だったのは、794年から1869年まで。東京へ都を移して150年程経ちます。しかし、約1,000年という長い間都だった京都からしたら、天皇さんはほんの少し京都を留守にしているといった感覚なのでしょう。
さて、桃の節句ですが、京都市京セラ美術館では、北沢映月の《娘》(1935年)を所蔵しています。雛祭を楽しむ姉妹の様子が描かれており、雅やかではんなりとした情感がただよいます。床に敷かれた毛氈には桃の花が飾られており、同じ毛氈の上には犬張子や雛人形の着物の裾が描かれています。
 画像4 北沢映月《娘》(1935年)
画像4 北沢映月《娘》(1935年)
京都出身の女性画家である北沢映月は53歳の時(1960年)に拠点を東京へ移します。上京後「上方の女を描けるのは貴女しかいない」と言われた映月は、それを天の啓示のように受け取り、自分が京女であることをより自覚して、終生東京に居を置きながら京都の女性を描き続けました。その原点でもある京都在住の28歳の時に京都市展に初入選した《娘》では、雛人形を東京で主流となっていた段飾りではなく上方の伝統的な平飾り(段飾りではあまり見られない犬張子が描かれている)[4]にしており、京都らしい“いけず”さを感じます。また、桜でも橘でもなく、桃の花を描いた点から、京女として生きた北沢映月にとって、桜よりも“桃”の方が京都らしいものだったのかもしれません。
おわりに
“桜”は日本の国花であり、時代を超えて日本人に愛されている花です。毎年ニュースで開花が予想され、硬貨や紙幣にも用いられています。
そして、京都に住む人にとっても、春の桜は日常の一部です。彼らは、桜の写真は撮っても「桜と〇〇」といった観光記念的な写真を撮ることはあまりないように思います。なぜなら、それらが日常生活の中にある風景だからです。その一方で、あらゆる芸術家や国内外から訪れる観光客はそれらを格別に美しい光景だと感じて切り取り、非日常のものとして転換し、作品や写真等を通して拡散しています。古くは、浮世絵師の葛飾北斎が「諸国名橋奇覧 山城あらし山吐月橋」にて、京都嵐山の渡月橋を舞台にして満開の桜を描いています。このように、京都の春を象徴する「桜と〇〇」は普遍的なモチーフとして、時代を超えて選ばれ続けているのです。こうして、あらゆる人々の中で京都の“桜”が特別なものとして残っていきます。
ではなぜ、京都の“桜”は時代を経ても特別な光景として切り取られ続けるのか?その魅力は何なのか?
その答えを探るために、実際に春の京都を訪れてみてはいかがでしょうか。
[1] 日本の伝統的な染色技法の一つ。紙や布の上に彫り抜きされた型紙をのせ、色をつけない部分に防染糊を置き、顔料や染料などで色染めをする技法。糊を置いた所は防染されるため、色は染まらず、他は一様に染色される。色止めをし、干して仕上げられる。
[2] 888年第五十九代宇多天皇によって開創され、以後1000年にわたって皇子、皇孫が門跡(住職)を務めたことから「御室御所」と呼ばれるようになる。
[3] 結婚式とは別の日にウェディングフォトを撮影することで、前日に撮影することを「前撮り」、 後日に撮影することを「後撮り」という。
[4] 伝統的に上方では平飾りや御殿飾り(二段飾りで、上段の御殿に雛一対を置き、その他に官女・左大臣・右大臣・桜橘などを置き、座敷には天児・這子・犬張子・市松人形・御所人形・お公家様の調度品などを置く飾り方)が主流だった。
※掲載している画像1,4は、執筆者が撮影許可のある風景や作品を撮影したものです。画像2,3は、著作権者の使用許可を得ています。全て転載や二次使用はできません。
長尾衣里子
京都市京セラ美術館 学芸員。
武蔵野美術大学卒。ロンドンSotheby’s Institute of ArtにてContemporary Art修士課程を修了。2019年より京都市京セラ美術館の学芸員を務める。専門分野である現代アートの手法を用いて、主にコレクションの展示を企画・運営している。担当した主な展覧会は、「京都の美術250年の夢 最初の一歩:コレクションの原点」(2020年)、「コレクションとの対話:6つの部屋」(宮永愛子・髙橋耕平の部屋を担当)(2021年)、「コレクションルーム秋期:特集 身体、装飾、ユーモラス」(2022年)、「コレクションルーム夏期:特集 人間国宝 稲垣稔次郎 -遊び心に触れて-」(2023年)、「コレクションルーム夏期:特集 女性が描く女性たち」(2024年)など。